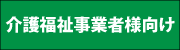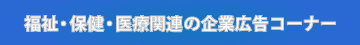�T�[�r�X��g�ݎ���Љ�
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ���@�{�݂̊O�� |
�n��j�[�Y�ɉ��������E�ۈ玖�Ƃ�W�J
�@���a54�N�ɐݗ����ꂽ�Љ���@�l�W�h������́A�uDO FOR OTHERS�v�i���҂ւ̍v���j�Ƃ����@�l���O�̂��ƁA�n��̉��E�ۈ�j�[�Y�ɉ��������l�Ȏ��Ƃ�W�J���Ă���B
�@�@�l�̉��v�Ƃ��ẮA�n��̕ۈ�{�݂��s�����Ă���Ƃ����j�[�Y���A�@�l�{���̂�����{��^�s�ɕۈ牀���J�݂������ƂɎn�܂�B���݂́A���G���A�A���ɁE�_�˃G���A�A�ޗǃG���A�ɂ����āA��쎖�Ƃł͓��ʗ{��V�l�z�[����F�m�ǃO���[�v�z�[���A�P�A�n�E�X�A�f�C�T�[�r�X�A�K����A���K�͑��@�\�^������ȂǁA�ۈ玖�Ƃł͔F�肱�ǂ����A�ۈ牀�i���j�A�n��q��Ďx���Z���^�[�A���ی㎙���N���u�Ȃǂ��^�c�B�@�l�S�̂̎��Ə�����46�J���ɂ̂ڂ�B
�@����ɁA�ߘa6�N4���ɂ͒n��ɂ������Q���x���̒��j�I�Ȗ�����S���u��^�s�����ǂ����B�x���Z���^�[�v�̖��c���ɂ������āA���@�l���܂ގЉ���@�l3�@�l���w��Ǘ��҂Ƃ��č̑�����A��Q�̂��邱�ǂ������̃��C�t�X�e�[�W�ɉ������A��ڂ̂Ȃ���т����x���̐��̍\�z�Ɏ��g��ł���B
�O���[�v�z�[���u���R���ǂ�v���J��
�@���@�l�́A�ߘa5�N3���ɓޗnj�����s�̌��厖�Ƃ̍̑����A�F�m�ǃO���[�v�z�[���u���R���ǂ�v���J�݂����B
�@�F�m�ǃO���[�v�z�[���̊J�o�܂ɂ��āA���������M�c�a�����͎��̂悤�ɐ�������B
�@�u����s�͌����ł�3�Ԗڂɍ���Ґl���������n��ł������A�M�ƂȂ���{�݂͏\���ɐ�������Ă��Ȃ�������܂����B����͂���ɔF�m�Ǎ���҂̑������\�������Ȃ��A�n��̃j�[�Y�ɉ��������Ƃ����z��������܂����B�܂��A�J�ݒn�̓���~�n���ɂ́A����20�N�ɊJ�݂������{�w���R���ǂ�x������A�V���[�g�X�e�C��f�C�T�[�r�X�A������x�����Ə��݂��Ă��܂����B����ɁA����31�N�ɂ͒n��̓����j�[�Y�ɑΉ����邽�߁A���{�w���R���ǂ�ʊفx���J�݂��邱�Ƃɂ��A���{�̓�������͂��킹��100�l�Ɋg�債�܂����B�n��̃j�[�Y�ɉ�����ƂƂ��ɁA����~�n���ɓ��{���^�c���Ă���X�P�[�������b�g���������Ȃ���A�F�m�Ǎ���҂̐g�̏�Ԃɉ������P�A�̒���{�ւ̏Z�ݑւ��ɂ��Ή����邱�Ƃɂ��A���p�҂��Z�݊��ꂽ�n��ŕ�炵��������悤�T�|�[�g���Ă��܂��v�B
�@�J�ݒn�́A�L���Ȏ��R�Ɉ͂܂ꂽ���ɂ���Ȃ���A�ߓS�����͂�Ȑ��u�w���k����w�v����k��10���ƍD���n�ɂ���B�ߗׂɂ̓X�[�p�[��z�[���Z���^�[�A���X�g�����E�J�t�F�Ȃǂ����闘���������n��ƂȂ��Ă���A���p�҂̉Ƒ����p�ɂɖʉ�ɖK����������Ƃ����B
|
|
|
| ���@�~�n���ɂ́A2 �J���̓��{�݂��A�d�x�ƂȂ����O���[�v�z�[���̗��p�҂̏Z�ݑւ��ɑΉ����Ă��� | ���@�����Ǒ�Ƃ��Đ�����ԂƐ藣�����ʉ��ݒu |
����~�n���̓��{�ƘA�g��}��
�@�O���[�v�z�[���u���R���ǂ�v�̌����́A�ؑ�2�K���Ă�1���j�b�g9�l�~2���j�b�g�̒��18�l�ƂȂ��Ă���B�{�ݐv�ł́A�p�i�\�j�b�N�Ђ��Ǝ��J�������u�e�N�m�X�g���N�`���[�H�@�v���̗p���A�ؑ����z�ł���Ȃ���A�ϐk���\�������A���z�R�X�g�ɂ��Ă��啝�ɗ}���邱�Ƃ����������B
�@�{�ݐv�̓��F����H������g�݂ɂ��āA�O���[�v�z�[���u���R���ǂ�v�Ǘ��҂̐��c�ۑ����͎��̂悤�ɐ�������B
�@�u���{�݂̂��鐶��s���R���́A�w��⤁i���Ⴙ��j�x�̒��Ƃ��Ēm���A�{�ݓ��̓V��͖ؖڂɂ���ȂǁA�a�����ӎ������f�U�C����������Ă��邱�Ƃ������ƂȂ��Ă��܂��B���p�҂ɂ������Ɖ߂����Ă��炤���߁A�L�����r���O��݂����ق��A�e������g�C���̔���F�������A���p�҂������Ŕ��ʂ��čs���ł���悤�H�v���Ă��܂��B�܂��A�F�m�ǂ������p�҂̎��_���d�����A��l�ЂƂ�̌��ɉ����������Ɏ��g��ł���A���N���i�Ɍ������؉������┃�����A�{�ݖK��Ȃǂ̊O�o�x���ɗ͂����A���@�l���^�c����ۈ牀�̂��ǂ������Ƃ̌𗬊���������I�ɍs���Ă��܂��v�B
�@����~�n���ɑ��l�ȉ��{�݂��^�c����X�P�[�������b�g����ʂƂ��ẮA���i�̋����w�����͂��߁A��Â��K�v�ȍۂɓ��{�ɕ��݂���f�Ï��Őf�@���邱�Ƃ��ł��A���{�ɂƂǂ܂炸�A�O���[�v�z�[���̗��p�҂ɑ��ă^�[�~�i���P�A��Ŏ��ɑΉ����邱�Ƃ��\�ƂȂ��Ă���B
�@�u�Z�ݑւ��̎���Ƃ��āA���v�w�œ����{�݂�T���Ă����P�[�X�ł́A����l�����{�ɓ������A������͗v���x���y�x�̂��߁A�O���[�v�z�[���ɓ������Ă����Ƃ���A����l���Ŏ����ɓ���A������̂��ōŊ����}�����������Ƃ����Ƒ�����̊�]������A���{����O���[�v�z�[���Ɉڂ��Ă��������A�Ŏ�����P�[�X������܂��B���̂悤�ɂ��Ƒ��̊�]�ɉ�������̂��A���݂�����{��f�Ï��ƘA�g���A��Â̒�Z�ݑւ��ɑΉ��ł��邱�Ƃ��傫���Ȃ��Ă��܂��v�i���c���j�B
|
|
|
| ���@�O���[�v�z�[���u���R���ǂ�v�̋����ƃ��r���O�E�L�b�`�� | |
 |
|
| ���@�e�K�̘L���̓V��͖ؖڂɂ���ȂǁA�{�ݑS�̂Řa�����ӎ������f�U�C����������Ă��� | ���@�~�n���ɍ؉�������A���p�҂��G�߂̖���͔|���邱�ƂɎ��g��ł��� |
�@�l�S�̂ŊO���l���E���̌ٗp�𐄐i
�@�@�l�S�̂̎��g�݂Ƃ��āA���@�l�ł͒����I�Ɉ��肵�ĉ��T�[�r�X����邱�Ƃ�ڎw���A�O���l���E���̐ϋɓI�Ȍٗp�𐄐i���Ă���B�ߘa6�N7�����݂�160�l�̊O���l�E�����ݐЂ��Ă���A�ݗ����i�ʂ̔z���Ґ��́A�ݗ����i�u���v86�l�AEPA��앟���m4�l�AEPA��앟���m����25�l�A����Z�\38�l�A���̑��i�i�Z�ҁA��Z�ҁA���{�l�z��ҁj7�l�ƂȂ��Ă���B
�@�u����21�N�ɏ��߂�EPA��앟���m���҂̎�����J�n�����Ƃ��́A���ۍv���Ƃ����Ӗ��������傫���A�����͗{���Z���ʓI�ȋ��l�œ��{�l�̉��E�����m�ۂ��邱�Ƃ��ł��Ă��܂����B�������A����28�N�ȍ~�ɉ��{�݂𗧂đ����ɊJ�݂����Ƃ���A�l�ފm�ۂ��傫�Ȗ��ƂȂ�A�O���l���E����ϋɓI�Ɏ������j�Ƃ��܂����B�����ŁA���{�݂̐V�݂ɂ��ẮA3����1�͏]���ʂ�̋��l�œ��{�l�E�����̗p���A3����1�͖@�l���̐l���ٓ��A�c���3��1�͊O���l�E�������p���邱�Ƃ��l���܂����B�����A�����͓���Z�\���Ȃ��A�V�݂̉��{�݂ɊO���l�E����z�u���邱�Ƃ��ł��Ȃ��������߁A�����{�݂ŊO���l�E�����̗p���A���{�l�E�����ٓ����₷����������܂����v�i�M�c�������j�B
�@���݁A���@�l�̉�암��ɏ�������E������1,000�l�̂����A�O���l�E���̊�����16�����߁A�o�g���ʂł́A�C���h�l�V�A��70�l�𒆐S�ɁA�t�B���s��47�l�A�x�g�i��28�l�A�~�����}�[8�l�A����3�l�A�l�p�[��2�l�A�^�C�A�u�[�^���e1�l�Ƒ��l�ȍ��Ђ̐E�����ݐЂ��Ă���B
�@�u�O���l�E���̓����Ԃ�Ƃ��ẮA�Ƃ��ɃC���h�l�V�A�A�t�B���s���A�x�g�i���Ȃǂ̍��͑�Ƒ���`�ł���A����҂ɑ��Čh�ӂƐe���݂������Đڂ��Ă���邽�߁A���p�ҁE�Ƒ��A�E���Ƃ̃R�~���j�P�[�V�������ǍD�ŁA�{�ݑS�̂̕��͋C�𖾂邭���Ă���Ă��܂��BEPA���҂͉�앟���m�̎擾��ڎw���ē������Ă��邽�߁A���̎d�����w�Ԉӗ~�������A���{�l�E�����G������āA�o�����h�����Ă��܂��v�i�M�c�������j�B
 |
 |
| ���@�ߘa6�N7�����݁A�@�l�S�̂�160�l�̊O���l�E�����ݐ� | ���@���p�҂̃P�A���s���O���l�E���̗l�q |
�����x���E�w�K�x���̎��g��
�@�O���l�E���ւ̎x���̐��ł́A�e�{�݂ɊO���l�E�������x������z�u���A���N�̎���m�E�n�E�����������ׂ₩�Ȏx�����s���Ă���B
�@�x�����e�Ƃ��ẮA�������̑��}���͂��߁A�Ƌ�E�Ɠd������������Z���̒i�t�q���ݏZ��Ɩ@�l���_�������j�A���I�葱����e�탉�C�t���C���A�g�ѓd�b���̌_��Ɋւ��铯�s�x���A�؍݉Ƒ��ւ̎x���i�ꍑ����̌Ăъ̉����A�ۈ珊�̏����j�A���{��E���i�擾�̂��߂̊w�K�x���Ȃǂ����{���Ă���B
�@�O���l�E���ւ̔z���Ɗw�K�x���̎��g�݂ɂ��āA�u���R���ǂ�v�O���l�E�������x�����̍������q���͎��̂悤�ɐ�������B
�@�u�O���l�E���ɂƂ��Ă�����̕s���͓��{��ɂȂ�܂��B�������Ȃ�������A���{���L�̞B���ȃj���A���X�Řb���ƁA�������邱�Ƃ������̂ŁA�h�₳�������{��g�ŊȌ��ɓ`���邱�Ƃ�S�����Ă��܂��B�ꍑ�̕�����K���A�@����̔z�������Ȃ��琶���̎w���ƃT�|�[�g���s���A�C�y�ɑ��k���Ă��炦��悤�ȊW�������邱�ƂɎ��g��ł��܂��B�܂��AEPA���҂ɑ��ẮA���{��̏K���ƍ��Ǝ�����̍u�`���A�Ǝ��ԓ��ɏT4���Ԋm�ۂ��Ă��܂��B���Ǝ������O��3�N�ڂ�12�`1���ɂ͎��K���Ԃ��܂߂Ċw�K���Ԃ��T18���ԂɊg�債�A�����ɗՂ�ł��������Ă��܂��B���̂ق��ɂ��A�z����́w���E�����C�Ҍ��C�x�ƂƂ��ɁA��앟���m���Ǝ����̎v���ƂȂ�w��앟���m�����Ҍ��C�x�̎�u�x�����s���Ă��܂��v�B
�@����ɁA�O���l�E���̃L�����A�A�b�v�ɂ����g�ނ��Ƃɂ��A���j�b�g�̃T�u���[�_�[�Ȃǂ̖�E�҂߂�O���l�E���������{�݂ő��݂��Ă���A�O���l���m�Ŏw�����邱�Ƃ⓭�����`�x�[�V���������߂邱�Ƃɂ��Ȃ����Ă���Ƃ����B����͂���ɍ��ЁA�ݗ����i�Ɋւ�炸�A�L�����A�A�b�v�ł����������i�߂Ă����Ƃ��Ă���B
�O���l�E���̓��E��]�҂�����
�@�ߔN�A���@�l�ł͓��E����]����O���l��앟���m���璼�ڃ��[���ʼn��傪����P�[�X�������A�o�^�x���@�ւ�ė��c�̂����p�����ɒ��ڌٗp���邱�Ƃ��ł��Ă���Ƃ����B
�@�u�����̊O���l�E�����W�܂�v���Ƃ��āA�O���l�����̗̍p�ē����[�������Ă��邱�Ƃ�����܂����A��͂蓯���o�g���̐E���������ݐЂ��Ă��邱�ƂŁA�R�~���j�P�[�V������}��Ȃ���A�O���l���m�Ŏw���⑊�k�ł���������邱�Ƃ��傫���Ǝv���܂��B�����Ă���O���l�E���������̉Ƒ���m�荇���ɓ��@�l���Љ��P�[�X�����ɑ����Ȃ��Ă��܂��B�܂��A������K���ɑ��āA�\�Ȍ��葸�d����E��Â�������邱�Ƃɂ��A�C�X�������̕��ŃW���o�u�i���Ɋ����X�J�[�t�j�𒅗p�����Ɩ����F�߂��Ȃ����߂ɁA���{�݂��瓖�@�l�ɓ]�E����]���邱�Ƃ�����܂��B���l����F�߂������߂ɁA���{�l�E����Ώۂɂ������C���s���A���ꂼ��̍�������K�������L���邱�Ƃɂ����g��ł��܂��v�i�M�c�������j�B
�@�O���l�E����ϋɓI�ɍ̗p���A�n��̕����j�[�Y�ɉ����铯�@�l�̍���̎��g�݂����ڂ����B
|
|
|
| ���@�O���l�̓��E��]�҂ƃI�����C���ʒk���s���l�q | ���@���{���ɂ͊O���l�E�������F��Ɏg�p����X�y�[�X��ݒu |
�������E�̗{�����K�v
�Љ���@�l�W�h������
������ �M�c �a�� ��
 �@
�@�@�O���l�l�ނ̎�����ʂƂ��ẮA��͂�l�ފm�ۂ�������̃����b�g�ƂȂ��Ă��܂��B�ǂ����Ă��E�����s������ƁA�E����l������̋Ɩ����S���傫���Ȃ�A���E�ɂȂ���Ƃ������̃X�p�C�����Ɋׂ�܂����A�����Ȃ�O�ɊO���l�E�����̗p���Đl�����m�ۂ��邱�Ƃ��ł��Ă��܂��B
�@�܂��A���E���ɂƂǂ܂炸�A�Ō�E����P�A�}�l�W���[�̊m�ۂ��������Ȃ��Ă��܂��B�ߔN�͕�����{���Z�������Ă��邱�Ƃ�����A����͍ݐЂ��Ă���E���̂Ȃ��ŕ������E��{�����Ă������Ƃ��K�v�ɂȂ��Ă��܂��B
�����@�{�݊T�v�@����
| ������ | �M�c�@�a�� | �a�@�J�� | �ߘa5 �N3 �� |
| ������� | 18 �l | ||
| ���ݎ{�� | �u���R���ǂ�v�i���ʗ{��V�l�z�[���A�V���[�g�X�e�C�A�f�C�T�[�r�X�A������x���j�A�u���R���ǂ�ʊفv�i���ʗ{��V�l�z�[���A�V���[�g�X�e�C�j | ||
| �@�l�{�� | �y���T�[�r�X�z18 ���Ə��^�y�ۈ�T�[�r�X�z27 ���Ə��^�y��Q�����T�[�r�X�z1���Ə� | ||
| �Z�� | ��630-0101 �ޗnj�����s���R��8030 �Ԓn | ||
| TEL | 0743�|70�|1832 | FAX | 0743�|71�|2083 |
| URL | https://www.chidori.or.jp | ||
���@���̋L���͌������u�v�`�l�v2024�N11�����Ɍf�ڂ��ꂽ���̂��ꕔ�ύX���Čf�ڂ��Ă��܂��B
�@�@�������u�v�`�l�v�ŐV���̍w�ǂ�����]�̕��͎��̂����ꂩ�̃����N���炨�\���݂��������B