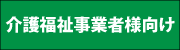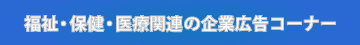�T�[�r�X��g�ݎ���Љ�
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ���@�{�݂̊O�� |
�n��̎q��ăj�[�Y�ɉ��������Ƃ�W�J
�@�R�����������S���a���ɂ���Љ���@�l���P��́A�u�q�ǂ��𒆐S�ɂ��Ƒ��̐S�Ƒ̂����ɂȂ��悤�Ȉ�Âƕۈ��ڎw���v�Ƃ����@�l���O�̂��ƁA�n��̎q��ăj�[�Y�ɉ�������I�Ȏx���Ɏ��g��ł���B
�@�@�l�̉��v�Ƃ��ẮA�����̏����~�}�̐����m������Ă��Ȃ��Ȃ��A����16�N�ɖ�ԁE�x���f�Ï��Ƃ��Ă̖�����S�����߁A�����̏����Ȉ�Ɛf�Â��J�n���A���N�Ɉ�Ö@�l�Вc���P��i�������E�{�{���F���j��ݗ��������Ƃɂ͂��܂�B����21�N�Ɍ��݂̊J�ݒn�Ɉړ]���āu���L�b�Y�N���j�b�N�v���J�@����ƂƂ��ɁA�b�{�s�ɂ��鏬�������~�}�Z���^�[���ғ��������Ƃɔ����A�f�Î��Ԃ�����ւƕύX���A�n��̏����Ȑ��f�Ï��փV�t�g�����B�����ɁA����~�n���ɔF�ۈ珊�u�����ۈ牀�v���J�݂��A��Âƕۈ����̓I�ɒ���̐������Ă���B����26�N2���ɎЉ���@�l���P���ݗ����A�ۈ玖�Ƃ��ڊǂ��Ă���A����30�N�ɂ͔F�ۈ珊����c�ۘA�g�^�F�肱�ǂ����Ɉڍs���Ă���B
�@����ɁA�n��̎q��Ďx���j�[�Y�ɉ����邽�߁A����22�N���珺�a���̈ϑ����ƂƂ��ĕa���ۈ玺�u�h���[���v�̉^�c���J�n�������Ƃɂ͂��܂�A����27�N�ɕ��ی㎙���N���u�u��߂���ԁv�A����28�N�ɏd�ǐS�g��Q���̓����ꎞ�a����{�݁u�X�}�C���v�A����30�N�Ɏq��Ďx���Z���^�[�u�Ȃ��ꐯ�v�A�ߘa6�N7���ɂ͎Y��P�A�Z���^�[�u�����v���J�݂��A�q��Ďx�����I�ɍs���̐����������Ă���B
�@�����̎��Ƃ͂��ׂē���~�n���Ŏ��{���Ă���A�����ȃN���j�b�N�Əd�ǐS�g��Q�������ꎞ�a����{�݂������A�Љ���@�l�Ƃ��ĉ^�c���Ă���B
�@��I�Ȏq��Ďx���Ɏ��g�o�܂ɂ��āA�Љ���@�l���P������E�����̋{�{�m�q���͎��̂悤�ɐ�������B
�@�u���Ƃ��ƁA���͍b�{�s�̕ی��t�����Ă��܂����B�����ȃN���j�b�N�̉@���ł���v��5�l�̂��ǂ�����Ă�Ȃ��A���܂��܂Ȏ{�݂ɂ��ǂ���a���Ă��܂������A�Ȃ��Ȃ��������a�������Ǝv����ۈ珊�ɏo����A�J�݂����̂������ɂȂ�܂��B�����A�����ȃN���j�b�N�݂����ۈ�{�݂͑S���ł����Ȃ������̂ł����A�J�����������ÓI�P�A�̕K�v�Ȃ��ǂ��̓���������Ă��܂����B�����g���q��Čo������a���ۈ�͕s�����Ɗ����Ă��܂������A�n�悩���ꂽ�q��ĂɊւ��鍢�育�Ƃɑ��A��ЂƂ����邩�����Ŏ��Ƃ�W�J���Ă��܂��v�B
���ǂ������̎�������⎩���S�����
�@����21�N4���ɊJ�������u�������ǂ����v�̒����75�l�ŁA���ǂ����m�̂ӂꂠ�����ɂ���c����ۈ�����{���Ă���B
�@�����̎��H����ۈ�̓��F�ɂ��āA�劲�ۈ狳�@������͂�ݎ��͎��̂悤�ɐ�������B
�@�u�����́A��Q���ۈ�Ƃ��Ĕ��B��Q��g�̏�Q�̂��ǂ���ϋɓI�Ɏ���A���p���S�̂�2���߂����߂Ă��܂��B���펙�Ə�Q�����ꏏ�ɐ�������C���N���[�V�u�ۈ��O��Ƃ��Ȃ���A���ǂ������̎�������⎩���S����ޕۈ�����H���Ă��܂��B�܂��A��Q���͎x���N���X�ł͂Ȃ��A�����N��̃N���X�Ő������Ă��邽�߁A���ǂ���������Q�����Ƃ��đ����A������O�̊��Ƃ��Ď���Ȃ���A���ǂ����m�ŏ����������Ƃ����R�ɍs���Ă��܂��v�B
�@���ɂ̐v�ł́A�����̏�Q��������Ă��邽�߁A�{�ݓ��͒i�����Ȃ��A�S�ʎł̉���ł͓���������n�C�n�C�ŗV�Ԃ��Ƃ��ł��A�����g��Ⴢ̂��邱�ǂ��ƌ��펙���ꏏ�ɎŐ��̂����ŐQ����тȂ���V��ł�����i������ƂȂ��Ă���Ƃ����B
�@�V�Y���͓����L���̕�����3������A�d��˂ŋ��ꂽ�e�������Ȃ����ƂŁA�G�ߍs���Ȃǂ̃C�x���g�Ɋ��p�ł���z�[���ɂ��邱�Ƃ��\�ƂȂ��Ă���B
|
|
|
| ���@�u�������ǂ����v��1�Ύ��N���X�̕ۈ玺 | ���@�S�ʎł̉���ł́A���ǂ����������S���đ���������A����������n�C�n�C�ŗV�Ԃ��Ƃ��ł��� |
|
|
|
| ���@�V�Y���́A�����L���̕�����3������A�d��˂ŋ��ꂽ�e�������Ȃ����ƂŁA���܂��܂ȃC�x���g�Ɋ��p���邱�Ƃ��ł��� |
�N���j�b�N�ƘA�g���A���ǂ��̔��B��S�̐����������
�@�����ȃN���j�b�N�Ƃ̘A�g�ł́A����ł���@���ɂ�邱�ǂ������̌��N�f�f��N3����{���A�̂̐��������łȂ����B��S�̐�����������Ă���B�C�ɂȂ邱�Ƃ�����ꍇ�ɂ́A�ی�҂ɓ`����ƂƂ��ɏЉ����o���A�����ɐ��@�ւɂȂ����ƂŁA��l�ЂƂ�̓��������ɂ߂Ȃ���A�X���[�Y�ɏ��w�Z�ւ̏A�w���ł���悤�x�����Ă���B
�@����ɁA�N���j�b�N�̏����Ȉ�ł���@���́A�A�����M�[����ł�����A�ۈ�{�݂ɂƂ��Ă͐H���A�����M�[�ւ̑Ή����傫�ȉۑ�ƂȂ�Ȃ��A�K�Ȉ�Ï��̂��Ƌ��H�̒�H��Ɏ��g�ނ��Ƃ��\�ƂȂ��Ă���B�ŐV�̏����Ȉ�Â̏�����邱�Ƃ́A���ǂ���ی�҂����łȂ��A�E�������S���ĕۈ���s�����ƂɂȂ����Ă���Ƃ����B
�@���̂ق��ɂ��A�����ł͊J��������̎��g�݂Ƃ��āA�ی�҂�Ώۂɂ����ۈ�Q����N1����{���Ă���B
�@�u�ۈ�Q���́A�����ɂ��v�w�ŗ������Ă��炢�A�O�V�т⋋�H���ꏏ�ɐH�ׂ���A�Q�����������āA���ǂ������Q�����Ă��鎞�Ԃɍ��k������Ă��܂��B1����ɎQ������ی�҂������ƕۈ�Q�ςɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�e�N���X��1�`2�g�ɂ��邱�Ƃł��ǂ��Ɗւ��@��𑝂₵�Ă��܂��B�ۈ�Q���̂˂炢�Ƃ��ẮA�ۈ�m�Ƃ��ǂ��̕��i�̊ւ������݂Ă��������A�ی�҂Ɉ��S���Ă��炤���Ƃ�����܂��B�܂��A�ی�҂������⑼�l�̂��ǂ��ɑ��A�ǂ̂悤�ɐڂ���̂����m�F���邱�ƂŁA���������ی�҂𗝉�����@��ɂ����Ă��܂��B����ɁA���ǂ����g���e�ɐ��������p���݂������Ƃ����ӗ~�ɂȂ���ȂǁA�O�҂ɂƂ��ĈӖ��̂��銈���ƂȂ��Ă��܂��v�i�{�{�����j�B
|
|
|
| ���@�����ȃN���j�b�N�݂��A�ۈ�ƈ�Â̗��ʂ���q��Ă��x�����Ă��� | |
�a�@�ۈ�͔N��1,000�l�̕a���i���ׁj������
�@���10�l�̕a���ۈ�ł́A�q��Čo���̂���ۈ�m��z�u���A�N���j�b�N�̊Ō�t��1��3��̏�Ԃ̊m�F���s���A�f�@���K�v�ȏꍇ�ɂ͂����ɏ����Ȉ�ɐf�Ă��炦�邽�߁A�ی�҂����łȂ��A�ۈ�m�����S���Ă��ǂ���a���邱�Ƃ��ł��Ă���B
�@�����A�a���ۈ�̗��p�Ώۂ͏��a���̍ݏZ�҂Ɍ��肵�Ă������A�{�{�@���͑S���a���ۈ狦��̎R�����x�����Ƃ��āA���Ɠx�d�Ȃ�ӌ��������s���A�L�旘�p�������邱�ƂŁA����29�N��茧�S�悩��̗��p���F�߂���悤�ɂȂ�A���݂̔N�ԗ��p�Ґ��͉���1,000�l�߂��ɒB���Ă���Ƃ����B
�@�u����ɁA�R�����x���Ƃ��ĕa���ۈ�̗��p���i2,500�~�j�̌��ƂɊւ���v�]�����o�����Ƃ���A�ߘa6�N10�����猧�Ǝs��1,000�~�S���A1,500�~�ŗ��p�ł���悤�ɂȂ�܂����B�a���ۈ�̍L�旘�p�͎R�������S�����ŁA�⏕�����n�݂����ȂǁA�q��Ă��₷���܂��Â��肪�i�߂��Ă��܂��v�i�{�{�����j�B
�@���̂ق��ɂ��A�����ł͌��펙�Ɍ��炸�A���B��Q��g�̏�Q�������ǂ��������������ی㎙���N���u��A�ی�҂̃j�[�Y�ɂ��킹�āA���ǂ��������ꎞ�a���莖�Ƃ����{���Ă���B
|
|
| ���@�a���ۈ�́A�����S�悩��N��1,000�l�߂��̗��p������ |
�d�S���̈ꎞ�a���莖�Ƃ��J�n
�@�d�ǐS�g��Q���̓����ꎞ�a����{�݁u�X�}�C���v�́A�����ȃN���j�b�N�ŖK��f�Â��s���Ȃ��ŁA�d�x�̏�Q���������̉Ƒ����敾���Ă���p��ڂ̓�����ɂ��A���X�p�C�g�P�A�̕K�v�������������Ƃ��畽��28�N�ɊJ�݂����B�����A�d�ǐS�g��Q����a����{�݂͖��Ԃł͌������ł������Ƃ����B
�@�u�w�X�}�C���x�̒����2�l�ŁA�Ō�t�ƕۈ�m��z�u���A�K�v�ɉ����ĊŌ�t���\ႋz����o�ljh�{�A�C�ǐ؊J�A�l�H�ċz��ɂ��_�f�Ö@�Ȃǂ̈�ÓI�P�A���s���Ă��܂��B�ۈ�m���X�L���V�b�v��}��Ȃ���A���t���ĉ̂��̂�����A�G�{�̓ǂݕ�������슈���Ɏ��g��ł��܂��B����ƁA�}���ɗ����ی�҂��w���펙�Ɠ����̌����������������̂ł��x�Ɨ܂��邱�Ƃ�����܂��v�i���쎁�j�B
�@�u�X�}�C���v�ł́A�e�̃��X�p�C�g�ƂƂ��ɁA�e�����痣��Đ�������ȂǁA���܂��܂Ȍo����ςނ��Ƃŏ����ɔ�����ړI�Ō����S�悩�痘�p����Ă���Ƃ����B
|
|
| ���@�d�ǐS�g��Q�������ꎞ�a����{�݂ł́A�Ō�t�ɂ���ÓI�P�A���s���Ă��� |
���l�Ȏq��Ďx���Ɏ��g��
�@����30�N�ɊJ�݂����q��Ďx���Z���^�[�́A��Q�̗L���ɂ�����炸���A�w���̐e�q�̒N�����ʂ���q��đ��k��V�сA�𗬂̏�Ƃ��ĉ^�c���Ă���B
�@�������e�ł́A����V�т�슈���A����ɂ��u���A���B��Q�̂��ǂ�������e�̍��k��Ȃǂ��s���ق��A���߂Ĉ玙������1�Ζ������̕�e��ΏۂɁA�q��Ă̔Y�݂�������h�{�m�ɑ��k���Ȃ���A���ԂÂ�����s���u�q��Ă��v���O�����v�����{���Ă���B
�@����ɁA�ߘa6�N7���ɎY��P�A�Z���^�[�u�Ȃ��ꐯ�v���J�݂��A�N���j�b�N�Ƌ������ĕ�q�̐S�g�̃P�A���s���Y��P�A���Ƃ��J�n�����B
�@�u���{�݂����鏺�a���́A�]�Α��̕��������A�R���i�Ђŗ��A��o�Y���ł��Ȃ��������Ƃ�����A�玙�ŌǗ����Ă����e�����Ȃ�����܂���ł����B�����ɂ�������̎Y��P�A�Z���^�[�͐���4�J���܂ł̎���ł���̂ɑ��A���Z���^�[�ł͐���1�N�܂ŗ��p�ł��邱�Ƃ��傫�ȓ����ƂȂ��Ă��܂��B���傤��������a��������ꍇ�ɂ��A���݂���ꎞ�a�����a���ۈ�𗘗p�ł���̂ŁA��e�ɂ������Ƌx�����Ƃ��Ă����������Ƃ��ł��܂��B�܂��A�q��Ďx���Z���^�[�Ɠ����t���A�ɐݒu���邱�ƂŁA��e���m���𗬂�}��A���ԂÂ��肪�ł�����������Ă��܂��v�i�{�{�����j�B
�@�����̑��l�Ȏq��Ďx�����Ƃ��^�c���邱�Ƃ́A���p�҂����łȂ��X�^�b�t�ɂƂ��Ă��悢�e���������炵�Ă���Ƃ����B
�@�u���{�݂ł́A�S����̃X�^�b�t���W�܂�E����c���s���A�e����̏�ۑ�����L���Ȃ���A���ʗ�����}�邱�ƂɎ��g��ł��܂��B���܂��܂Ȏx���ɂ��Ċw�ׂ邱�Ƃ́A�X�^�b�t�̎��삪�L����A�P�A�̎������߂邱�ƂɂȂ����Ă��܂��v�i���쎁�j�B
�@���ǂ��ƕی�҂̑̂ƐS�����ɂ����I�Ȏq��Ďx�����s�����@�l�̎��g�݂��A��������ڂ����B
|
|
|
| ���@�ߘa6�N7���ɊJ�݂����Y��P�A�Z���^�[�u�����v�B�����t���A�Ɏq��Ďx���Z���^�[�u�Ȃ��ꐯ�v���^�c���A��e���m���𗬂���@��������� | |
�ۈ�̎d�������X�y�N�g����Љ�K�v
�Љ���@�l���P��@�������ǂ���
�������E���� �{�{ �m�q��
�@���݂̉ۑ�Ƃ��ẮA�����₷���E��Â���Ƃ��ĐE����p�̋x�e����݂�����A�\���ȋx�e���Ԃ̊m�ۂɎ��g��ł��܂����A�ۈ�m�̐l�ފm�ۂƒ蒅�͌������ɂ���܂��B
�@����ɁA���̗v���Ƃ��ĕی�҂̂Ȃ��ɂ͕ۈ���T�[�r�X�ƂƂ��đ����A�ߏ�ȗv���������P�[�X�������Ă���A�^�ʖڂȐE����ۈ�Ɏv�����ꂪ����E���ł���قǁA����J���Ƃ��Ĕ敾���Ă��܂��Ƃ��낪����܂��B��������̉��P���d�v�ł����A�ۈ�̎d���ɑ��ă��X�y�N�g���Ă����Љ�ɂȂ�Ȃ���A�ۈ�m���u���l�ނ𑝂₵�Ă������Ƃ͓���Ɗ����Ă��܂��B
�����@�{�݊T�v�@����
| �������^���� | �{�{�@�m�q | �a�@�J�� | ����21 �N4 �� |
| ��� | 75 �l | ||
| ���ݎ{�� | ���L�b�Y�N���j�b�N�i�����ȁA�A�����M�[�ȁj�A�d�ǐS�g��Q�������ꎞ�a����{�݁u�X�}�C���v�A�a���ۈ玺�u�h���[���v�A�q��x���Z���^�[�u�Ȃ��ꐯ�v�A���ی㎙���N���u�u��߂���ԁv�A�Y��P�A�Z���^�[�u�����v�A�ꎞ�a����u�ɂ��ɂ�����ԁv | ||
| �Z�� | ��709-3863 �R�����������S���a���͓�����748�|2 | ||
| TEL | 055�|268�|5577 | FAX | 055�|268�|5598 |
| URL | https://www.genkikids-clinic.com/ | ||
���@���̋L���͌������u�v�`�l�v2024�N12�����Ɍf�ڂ��ꂽ���̂��ꕔ�ύX���Čf�ڂ��Ă��܂��B
�@�@�������u�v�`�l�v�ŐV���̍w�ǂ�����]�̕��͎��̂����ꂩ�̃����N���炨�\���݂��������B